| ■ 「運・鈍・根」と「無用の用」 |
 |
10月6日のノーベル生理学・医学賞の坂口志文先生に続き、8日のノーベル賞科学賞でも北川進先生が受賞しました。今年は既に日本人二人目の受賞で、これで30人目になります。 同じ年に異なる部門で受賞したのは2部門・2人(2015年)が過去一回あるだけだそうです。 |
|
| 本当におめでとうございます! | 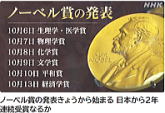 |
|
| ■ 「運・鈍・根」と「無用の用」 |
 |
10月6日のノーベル生理学・医学賞の坂口志文先生に続き、8日のノーベル賞科学賞でも北川進先生が受賞しました。今年は既に日本人二人目の受賞で、これで30人目になります。 同じ年に異なる部門で受賞したのは2部門・2人(2015年)が過去一回あるだけだそうです。 |
|
| 本当におめでとうございます! | 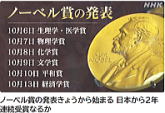 |
|
| テレビ番組で知った話ですが、ノーベル賞科学賞の北川先生は、学生たちに常々語っている「運・鈍・根」の実践的な哲学があるそうです。 *運 :「運は準備された心に宿る」というパスツールの言葉を引用し、偶然の発見も日々の積み重ねが引き寄せる。日々の積み重ねがなければ引き寄せることもない。 *鈍 :「すぐに答えを出さず、立ち止まって考え続ける力」が必要である。わからないことにしぶとく向き合う姿勢が大切である。 *根 :「10年後に評価される研究でもいい」“強い思い”をもって、長期的視点で粘り強く取り組むことが重要である。 |
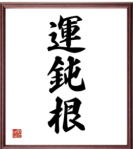 |
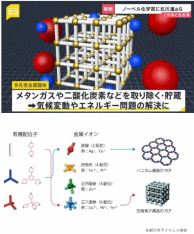 |
北川氏はMOF(多孔性金属有機構造体)の研究で世界的な成果を挙げましたが、初期は「つまらないイオン」とされる銅1価を扱っていました。 研究中、学生が「孔が空いています」と言ったとき、普通なら「電気が流れないなら意味がない」と否定するところを、「空間が面白い」と直感し、そこから新しい分野を切り拓いたそうです。 北川氏は学生に「失敗だと思ったとき、それは面白い発見かもしれない。立ち止まり、考え続けることが大切だ。運は準備された心に訪れる。」と常々語っているとのこと。 この考え方は、単なる研究者への助言にとどまらず、人生の選択や困難への向き合い方にも通じるものだと思いました。 |
|
座右の銘は「無用の用」とのこと。 |
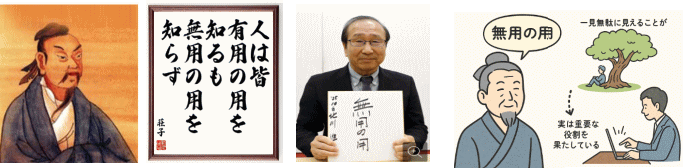 |