| 『吉田松陰ゆかりの地を巡る旅』を萩観光協会に相談しながら2週間かけて企画し、いろいろ事前予約をした上で、7月7日・8日で行ってきました。 吉田松陰の生きた時代と松陰の思想を、より深く理解できた密度の濃い2日間でした。まだその時の余韻が心身に残っている感じです。 一番印象深かったことは、当初は全く想像してもいなかった『松陰神社に正式参拝して、松下村塾の講話室で宮司の講話を聴くこと』です。(2日目) |
 |
|
■『吉田松陰ゆかりの地を巡る1泊2日の1人旅』その① |
| 『吉田松陰ゆかりの地を巡る旅』を萩観光協会に相談しながら2週間かけて企画し、いろいろ事前予約をした上で、7月7日・8日で行ってきました。 吉田松陰の生きた時代と松陰の思想を、より深く理解できた密度の濃い2日間でした。まだその時の余韻が心身に残っている感じです。 一番印象深かったことは、当初は全く想像してもいなかった『松陰神社に正式参拝して、松下村塾の講話室で宮司の講話を聴くこと』です。(2日目) |
 |
| まずは松陰神社本殿で一人だけ座って、禰宜による太鼓で始まる祝詞奏上、そして私が榊奉納し“2礼2拍手1礼”する儀式に加えて、神殿脇で御神酒をいただくという、本格的参拝をしました。そのあと白上宮司から“松陰神社の由来や歴史”なども紹介していただきました。 松陰神社に正式参拝のあと、『一般観光客は立ち入ることができない松下村塾の講義室』で、白上宮司から吉田松陰にまつわる話を聴きながら質疑応答にも対応していただきました。最高に贅沢な講義を受けることができました。 実は、私から共育塾で話しているプラスワン資料「日本を明治維新に導いた学問/朱子学・陽明学から学ぶ」を宮司に事前郵送しており、この中には吉田松陰に関して“松下村塾の基本思想” などを含めて見ていただいています。(宮司はその資料を持参されていました) 今回は白上宮司から、吉田松陰の思想形成のプロセスを含めて、たくさんのことをご教授いただきました。 |
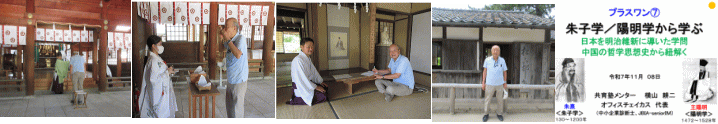 |
| 吉田松陰は6歳で吉田家の養子となり、吉田家のお役目『兵法(山鹿流)師範』を継承し、理解しきれないまま厳しい修行を積むことからスタート。尊王敬神(皇室重視)の精神を叩き込まれて神道も学んだあと、朱子学、水戸学、国学、倫理哲学、歴史伝記、地理紀行、医学など幅広く書物から知識を得ようとしたそうです。ちょうど朱子学に疑問を感じはじめた頃、肥前平戸藩に旅をした折に書物「伝習録(王陽明)」を借り受けて、陽明学の思想に触れたことが思想形成に大きかったとのこと。儒学から派生した朱子学(保守:性悪説)と陽明学(革新:性善説)のうち、どうも松陰は陽明学のほうに共感する面が多かったようです。 | 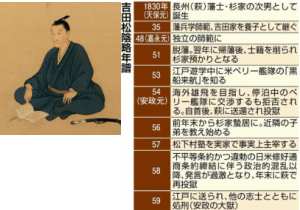 |
| 宮司の話では「吉田松陰を陽明学者と言う人も多いが、多くの学問を融合した“吉田松陰思想”を構築した思想家です」との考え方には、私も強く共感しました。 |
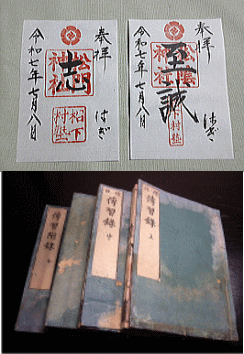 |
松陰神社の御朱印文字は「志」と「至誠」の二つがあります。これは“吉田松陰の思想の原点は「志」と「至誠」の二つにある”という松陰神社の考え方だと解釈しました。 宮司からご教授いただきましたが、一言で表すと『立志』であるとの話でした。「立志」とは「心の不純物を取り除くこと(純化、浄化)」「聖人君子の本を読むこと」そして「大切なのは量でなく質である」とご教授いただき、私も共感した次第です。松陰の言葉に『学は人たる所以を学ぶなり』が有名です。 そして松陰思想の具体事例を聴いていく中で、私が「現代でいうと稲盛和夫の哲学に近いように感じます。」と話したところ、「商工会の方から“京セラフィロソフィーを読んでみませんか”と勧められ、初めて読んでみたところ実は私も同じことを感じました。」との話でした。裏話ですが、稲盛和夫が亡くなる前日まで読んでいた終生の書は「伝習録」だそうです。 |
| 私の理解不足を実感するとともに、宮司と意気投合することが多々あり、私のとって非常に密度の濃い、有意義な時間を持つことができました。今回の小旅行で、あまりにも多くの吉田松陰の多様な実像情報に触れたので、シリーズ投稿しながら、少しづつ理解を増やしていきたいと思います。 |