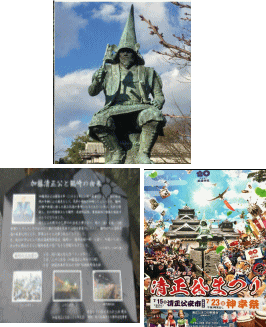| 税理士の平岡さんから、熊本に関する珍しい話を聞きました。 「江戸時代初期に肥後藩の“飛び地”が豊後国(鶴崎や佐賀関)にあった」とのこと。 関ヶ原の戦いの功績により、徳川家康は加藤清正に肥後藩北部と天草を領地に与えましたが、清正は天草を辞退し、天草の代わりに大分の鶴崎や佐賀関を所領として求めて、“飛び地”を認め与えられた。具体的には直入郡(久住・白丹)、大分郡(鶴崎・野津原・三佐)、海部郡(佐賀関・大在)の3地域だそうです。 これらの地域は、明治維新後の廃藩置県(1871年)まで、肥後藩の“飛び地”として存在していましたが、その後、廃藩置県により大分県に編入されました。 「なぜ天草拝領を辞退したのか?」「なぜ飛び地を求めたのか?」に、非常に興味を持ち、早速コパイロットを使って調べてみました。 加藤清正が天草の領地を辞退し、代わりに大分の鶴崎や佐賀関を所領として求めた理由として、大きく下記の3要因があったようです。 |
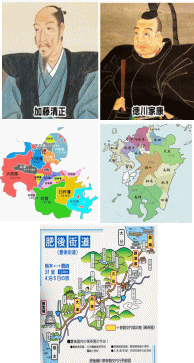 |
| *地理的要因 : 天草は島嶼部であり管理や防衛が難しい地域。一方、鶴崎は瀬戸内海・豊後水道に面した海上交通の要所で、経済的な発展が期待できる場所だった。 *経済的要因 : 鶴崎は港町であり、商業活動が盛んでした。清正はこの地を発展させることで、藩の経済基盤を強化につながると考えた。 *政治的要因 : 天草はキリシタン大名である小西行長の影響が強く、宗教的な対立が生じる可能性があった。清正はこれを避けるために天草を辞退した。 |