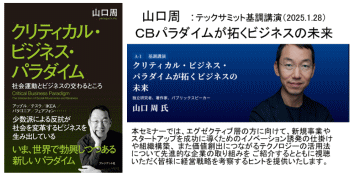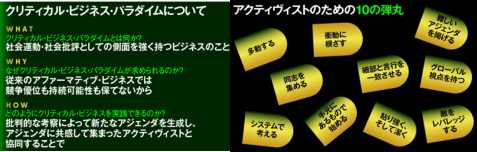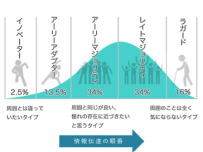クリティカルとは、「重大な」「決定的な」という意味を持つ形容詞「critical」をもとにした外来語です。批評家などを意味するラテン語「criticus」が語源とされており、「批判的な」「危機的な」という意味でもcriticalが使われます。(後者はビジネスシーンで使われる) 「クリティカル・シンキング」は、批判的な思考を表した言葉です。この場合の批判的は、世間の常識を真に受けず「本当にそれでいいのか?」と疑ってみることを意味しています。 新しいアイデアの発見や課題の解決には、一つの考え方に捉われない柔軟性が不可欠です。そのためビジネスシーンでは、普段の行動や考え方をあらゆる角度から分析するクリティカル・シンキングが重視されています。 なお、論理的思考を表す「ロジカル・シンキング」とは意味合いが少し異なります。ロジカル・シンキングは推論を重ねた上で、納得のいく結論を導き出す思考プロセスを指した言葉です。 |
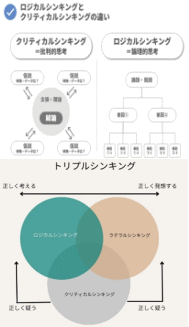 |