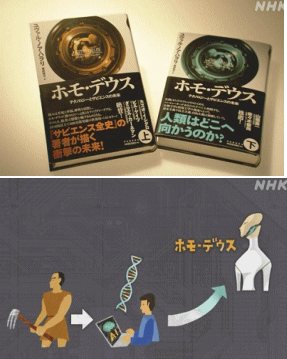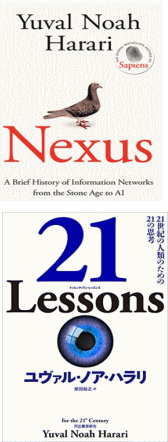| 生成AIの急激な変化&活用の広がりは、目を見張るものがあります。 NHKニュースウェブ(2024.8.27)より、NHK国際部デスク・豊永博隆氏の気になる投稿記事の「イスラエルの歴史学者ヴァル・ノア・ハラリ氏が語ったこと」を紹介します。 「我々は神の能力だと伝統的に考えられてきた力を入手する過程にある」 世界的なベストセラーとなった「サピエンス全史」の著者ハラリ氏は6年前、2018年に行った私とのインタビューでこう語った。AI=人工知能がもたらす脅威について、まるで予言するかのような指摘をした。 また今年9月にはAIを含む情報の過去と未来、情報と真実、情報と権力の複雑な関係を読み解く本を出すとのこと。 本のメッセージを大胆に予測しつつ、進化するテクノロジーとの向き合い方を探る。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240827/k10014559741000.html |
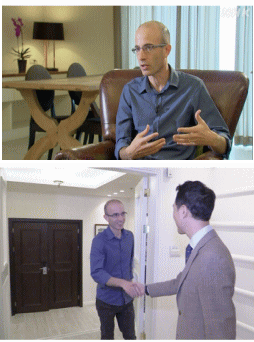 |