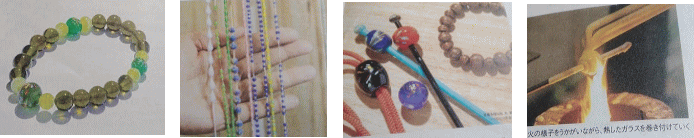 |
| ■和泉蜻蛉玉 |
| 蜻蛉玉とは、ひも通し穴が開いたガラス玉のことで手軽に身につけられるアクセサリーで可愛いくてカラフルなものがあります。かって和泉国と呼ばれた大阪府堺市で奈良時代以前から作られ「技術・技法・素材」を継承し、この地域で作られたものだけが
「和泉蜻蛉玉」と言われています。 通常の蜻蛉玉はガラス棒1本でつくるが数本を束ねて作るのが、和泉蜻蛉玉の特徴だそうです。 さまざまな色のガラスを同時に扱うことで、複雑な模様や色を組み合わせられるそうです。 熱して溶かす時もガスバーナーだと、高温のあまり急激な化学反応がおき色同士が美しく混ざり合わないので「カンテラ」の火で熱してとかすそうです。 昭和の中期ごろは、地域一帯で多くの人がガラスに関わる仕事をしていたそうだが、その後海外に技術が流失し、蜻蛉玉は一時存続の危機に。 その後伝統工芸士の松田有利子さんは、伝統を途絶えさせまいとその技法や歴史の調査、保存活動を実施。その結果大阪の伝統工芸として認定されたそうです。 専業で唯一の工房として今日に受け継いでいます。現在は、アクセサリーやお香立て、着物の帯留めをはじめ、酒造メーカーの商品に和泉蜻蛉玉のデザインを施すなど様々な新展開もみられるようです。これからも伝統を守って色々な蜻蛉玉を作られるのを楽しみにしています。 ダスキン喜びのタネまき新聞より |
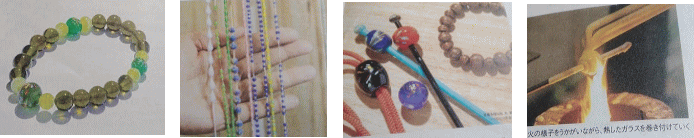 |