|
大正時代、山形県の「尾花沢の徳良湖」の築堤工事の際「土搗き唄(どんつきうた)」歌っておたがいを鼓舞しながら、息を合わせて作業を行う際に、歌に合わせて菅笠をくるくると回す即興のおどりが、現在、山形花笠まつりで披露される「花笠踊り」の原型だそうです
。花笠は、元来農作業の際に、日除けや雨よけに使われていたのを祭り用に華やかに装飾し造花を付けたり、踊っているときに音がなるようにと鈴を付けたりしました。 |
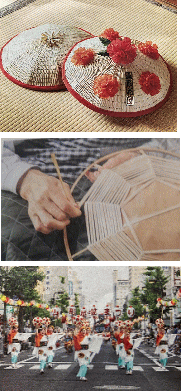 |
| ■花 笠 |
|
大正時代、山形県の「尾花沢の徳良湖」の築堤工事の際「土搗き唄(どんつきうた)」歌っておたがいを鼓舞しながら、息を合わせて作業を行う際に、歌に合わせて菅笠をくるくると回す即興のおどりが、現在、山形花笠まつりで披露される「花笠踊り」の原型だそうです
。花笠は、元来農作業の際に、日除けや雨よけに使われていたのを祭り用に華やかに装飾し造花を付けたり、踊っているときに音がなるようにと鈴を付けたりしました。 |
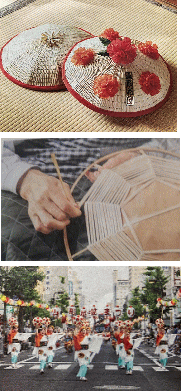 |